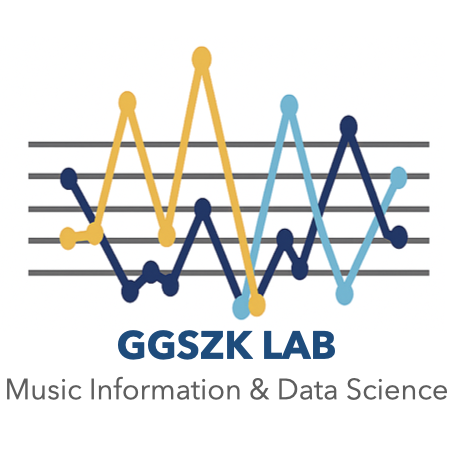
開志専門職大学 情報学部 鈴木研究室に関する情報発信サイトです.
お問い合わせは lab@ggszk.org までお願いします.(非公式)
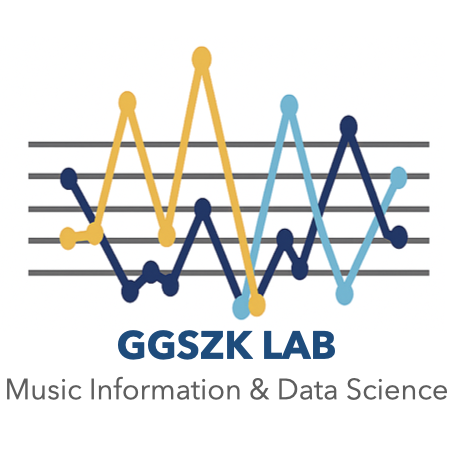
開志専門職大学 情報学部 鈴木研究室に関する情報発信サイトです.
お問い合わせは lab@ggszk.org までお願いします.(非公式)
この度,本研究室の木原優月くんが,地域社会におけるデジタルコンテンツの祭典「にいがたデジコングランプリ2025」のテクノロジー部門において,作品「アイラ(AI Learning Assistant):生成AIを活用したプログラミング学習環境」で,入賞を果たしました. 入賞作品のビデオは,以下のデジコングランプリ公式ページよりご覧いただけます. ▼ にいがたデジコングランプリ2025 入賞作品一覧 https://www.niigata-digicon.com/digicon/past/prize2025.html
4年生が取り組んでいるテーマ「天候依存度を活用した観光ルート推薦」に関連して,7/31に教員+学生1名で,新潟県観光協会を訪問し,意見交換を行いました. 新潟県観光協会は「にいがた観光ナビ」を運営しており,Tableauを利用したデータ分析など,積極的な情報発信で知られています. 今回の議論では,冬の佐渡には「船が出ない」という先入観があるものの,実際にはポテンシャルがあることなどが話題に上がり,観光地の天候依存度を可視化する意義を改めて確認できました. また,観光に関するデータ活用の難しさ(信頼性のあるデータ収集が難しい)も伺うことができ,今後の研究の重要な示唆となりました.引き続き検討を深め,新潟の観光に活かしていきます. 参考 にいがた観光ナビ
開志専門職大学は,JDLA(日本ディープラーニング協会)の賛助会員(Silver)になっており,協会の意志に賛同し,AI教育を実践しています.この(主に)会員向けのイベントであるJDLA All Handsに参加しました(7/29).理事長である松尾先生のお話など,最新のAI動向を把握することができました. 参考:日本ディープラーニング協会
7/27のオープンキャンパスで,「コンビニレシートのデータから読み解くお店の評判と売れ筋」のタイトルで,体験授業を実施しました.CODAPを使ったレシートデータからのグラフ作成や,トピック抽出を使ったコンビニの特徴発見,などの内容を,高校生が興味を持って取り組んでくれました.
新潟県国際情報高校のデータサイエンス科目のゲスト講師として,「高校生のためのデータサイエンス」の実習を実施しました.今回が3回目で,検定をテーマとして,学生アンケートの結果やJリーグの得点データを利用した差の検定と,ガチャシミュレーションを利用した比率の検定を体験してもらいました.
長野県飯山高校でオンラインのデータサイエンスに関する講義を行いました(7/11).Jリーグの得点データなどを参考に,データサイエンスとは何か・データサイエンティストの役割・データサイエンスにおけるモデルなどについて基本的な内容を話しました.
ゼミの4年生2名とともに、音楽情報科学研究会(第143回研究発表会)・SLP合同シンポジウムに参加しました。 今回は発表は行いませんでしたが、音楽に関する研究ポスターを中心に調査し、多くの刺激を受けました。 音楽認識、作曲支援、ライブ演奏支援、音楽と言語の関係など、幅広いテーマの研究が発表されており、学生にとっても貴重な学びの機会となりました。 音楽と情報技術のつながりに関心のある方には、非常におすすめのシンポジウムです。 🔗 シンポジウムの詳細はこちら(情報処理学会)
本ゼミの卒業生が、開志専門職大学キャリアセンターの特集記事および公式YouTubeチャンネルで紹介されました。 記事では、在学中に力を入れた学びや就職活動、現在の仕事にどのように大学での経験が活かされているかについて語っています。 また、動画では、卒業生の生の声を通して、大学での成長や今後の目標がわかりやすく紹介されています。 これから進路を考える在学生や、情報学分野に関心のある高校生にも参考になる内容です。ぜひご覧ください。 🔗 大学キャリアセンターでの紹介記事 ▶️ YouTubeでの紹介動画(開志専門職大学 公式)
2025年1月11日(土),情報学部4年 曽根歩生さん(鈴木ゼミ所属)が,情報処理学会ソフトウェア工学研究会主催「ウィンターワークショップ2025」(会場:海峡メッセ下関)にて研究発表を行いました. 本発表は,プログラミング教育におけるエディタログの活用とリプレイツールの試作についての研究成果を紹介するものです. ↓大学の広報記事 情報処理学会ソフトウェア工学研究会主催「ウィンターワークショップ2025」で発表!
2023年9月12日に,株式会社メビウス・開志専門職大学による共催のデータイノベーションフォーラムで,「小規模農家におけるデータ活用高度化に向けて-ベジ・アビオの事例(鈴木源吾(開志専門職大学情報学部)・斎藤順(新潟食料農業大学))」を発表しました. 大学の広報記事↓ データイノベーションフォーラムを開催しました。 イベントに関する情報↓ データイノベーションフォーラム イノベーションで未来はどう変わるのか